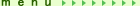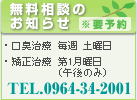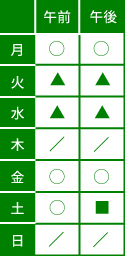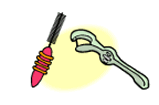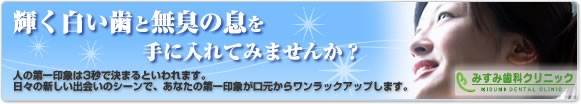|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
 |
みすみ歯科クリニックのほとんどの患者様は治療が終わると、虫歯や歯周病予防のための定期的なケア(おもに専門的なお口のお掃除や検査)に来院されます。たとえれば、美容室に行くような気楽な感覚で、安心して受けられますし、気持ちよかった、スッキリしたと喜んで帰られます。
ヨーロッパの予防先進国では既にこの考え方、システムは当たり前で、国民の口の中の多くの虫歯と歯周病は無くなりました。 削らない、抜かない、痛くない・・・気持ち良くって健康で長持ちできる「予防歯科」・・・
あなただけの「予防プログラム」をつくり、それを実行して、ムシ歯のない健康な歯列をつくりましょう。
当クリニックでは、インフォームドコンセントを徹底させております。
まず、診療スペースに入っていただく前に、カウンセリングルームにて患者様のお話を十分に伺ったうえで、具体的な治療に関する相談や説明を行います。
これまで、「恥ずかしくて、ドクターには聞けない」「他の患者さんに聞かれるのが恥ずかしくて、聞けない」「何がわからないんだか、わからない」など、多くの悩みを抱えていらっしゃった方も安心・納得して治療に望んでいたけます。
 |
|
顕微鏡で確認することによって、現在の状態はどうなのか、これからどうなっていくのか、が判断できます。 |
|
●菌の動きは活発かどうか。 ●菌の大きさはどうか。 ●菌の数は多いのかどうか。 |
|
ご自分のお口の状態を理解してもらうため、すべての患者様に持って頂き、毎回の治療内容を記入してカルテ代わりとして使っていただきます。 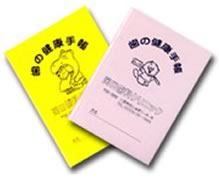 |
●子供用
乳幼児やお子様には、う蝕に対するリスク診断をおこない、健康な永久歯列の完成を目的としたプログラムを作成します。
●大人用
成人の方には、お子様の検査に加え歯周病の危険度を調べ、健康な歯と歯茎をどのように保つかを分析します。
| 子供用 | (1)虫歯の細菌検査 (2)唾液の緩衝能 (3)飲食の回数 (4)プラークの蓄積量 (5)唾液の質と量 (6)フッ素の使用状況 (7)虫歯の経験 |
大人用 | (1)〜(6)にプラス (7)喫煙本数 (8)危険因子の数 (9)歯周病進行度 (10)歯周病菌のチェック |
|---|
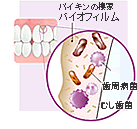 3DSとは、デンタル・ドラッグ・デリバリー・システム(Dental
Drug Delivery System)の略です。
3DSとは、デンタル・ドラッグ・デリバリー・システム(Dental
Drug Delivery System)の略です。
虫歯の原因菌は、ミュータンス菌と呼ばれる虫歯菌によって起こります。このミュータンス菌をお口の中から除菌できれば、虫歯の危険性を下げることが可能であることが国立感染症研究所の研究で明らかになりました。
ミュータンス菌はバイオフィルムという細菌膜を歯の表面に形成しており、飲み薬や塗り薬が直接効かない環境を作っております。
そこで、このバイオフィルムをPMTCで機械的に歯の表面から取り除き、ドラッグ・リテーナーと呼ばれるマウスピースを使ってPlak Out(抗菌剤)を安全かつ確実に作用させることにより、ミュータンス菌を除菌するのです。これが、3DSと呼ばれる虫歯菌を除菌する画期的な新技術なのです。
 「PMTC」を簡単に説明すると、毎日の自分で行なう歯磨きで落ちない歯の汚れを歯医者さんで専用機器を用いてきれいにクリーニングすることです。
知らず知らずのうちに磨き残してしまった部分や歯ブラシでは磨くことができない歯周ポケット(歯と歯肉の間のみぞ)内の歯の根の部分もキレイに磨き上げて汚れを取り除きます。歯質の強化による虫歯予防、歯の着色を除去し、光沢のあるきれいな歯を保つことができます。
使用するのはゴムやブラシなど柔らかい材質の物ばかりなので痛くはなく、むしろ気持ちがいいですよ!!
「PMTC」を簡単に説明すると、毎日の自分で行なう歯磨きで落ちない歯の汚れを歯医者さんで専用機器を用いてきれいにクリーニングすることです。
知らず知らずのうちに磨き残してしまった部分や歯ブラシでは磨くことができない歯周ポケット(歯と歯肉の間のみぞ)内の歯の根の部分もキレイに磨き上げて汚れを取り除きます。歯質の強化による虫歯予防、歯の着色を除去し、光沢のあるきれいな歯を保つことができます。
使用するのはゴムやブラシなど柔らかい材質の物ばかりなので痛くはなく、むしろ気持ちがいいですよ!!
 |
専用の器具を使って歯石を細部までとっていきます。 |  |
歯の表面や根元の部分を回転ブラシなどできれいに磨き上げる。 |  |
お口の中を洗って、歯質を強化するフッ素で歯の表面をコーティングします。 |
特に注意していただきたいのは、むし歯の病因菌(ミュータンス菌)は生まれたばかりの赤ちゃんの口の中にはいないことが確認されているにもかかわらず、歯が生え出す頃から次第に感染者が増加する事実です。 ミュータンス菌の量が多いお母さんとお子さんが、同じスプーンを使って食事したりするとミュータンス菌に感染しやすくなります。むし歯菌は、一般にWindow of infectivity「感染の窓」(生後19ヶ月〜31ヶ月)の時期に母親から感染すると言われています。また、お母さんに治療していないむし歯があると余計にミュータンス菌が増加しますので、早めに治療しましょう。 定期的に細菌検査を行い、除菌処置を繰り返すことをお勧めします。